今回の記事ではおせちにも地域差がある?具材の違いや特徴を紹介しています♪
毎年、いろんなお店から豪華なおせち料理が販売されますよね。
どれを選んでも間違いなく美味しそうなおせちばかりですが、実はおせち料理も地域によって違いがあるんですよ!
今回は地域によっておせちの中身がどう違うのか、特徴や具材をまとめています。
お正月、おせちを食べながら、ちょっとしたネタとして話題にしてみると盛り上がるかもしれませんよ(*’▽’)
おせちにも地域差がある?

おせちにも地域差があるのか、気になりますよね!
子どものころから、毎年慣れ親しんだおせち料理が当たり前かと思ったら、結婚などで引越してみたら、全然違っていてびっくりした!なんていうのはよく聞く話です。
おせちといえば定番の「数の子」「伊達巻」「黒豆」「栗きんとん」「昆布巻き」などがあります。
これらは比較的、どこの地域のおせちにも入っています。
そして、実はおせちの料理はお重によって、入れる段が決まっています。
どの段に入れても大丈夫!ではないんです。
おせち料理の段はいろいろありますが、正式には4段となっています。
一の重
一の重は「祝い肴」で黒豆、数の子、田作り、紅白かまぼこを入れます。
二の重
二の重は「口取り」といわれ、きんとん、伊達巻、昆布巻き、などの甘い物や紅白なますなどの酢の物を詰めます。
三の重
三の重は「焼き物」です。海老や魚などの海産物を詰めます。
与の重
四の重は四は死を連想し。不吉な数字のため、与の重とされています。
煮物やお煮しめなど山の幸を詰めます。
おせちはこのように、段によって意味があり、詰める料理も決まっています。
では、このお重の中身が東日本と西日本で、どのように変わるのか見ていきます。
おせちの地域差!東日本のおせちの具材は?
東日本と西日本では気温や自然が大きく違うこともあり、たくさんの違いがあります。
東日本と西日本のおせち料理で大きく違うのは、やはり味付けです。
お出汁の濃さが全然違うんですよ!
東日本では、濃口醤油を使った濃い目の味付けになっています。
他にも、お正月といえば、縁起の良い魚として食べられる年取り魚があります。
東日本の年取り魚は鮭が定番です。
鮭は寒くなる季節に、海から東日本の方に帰って来るため、9月〜11月頃に獲れた鮭を塩漬けにして保存したものをお正月に食べるそうです。
北海道では鮭を「氷頭なます」という料理にして食べます。
他にも、東北の中では岩手県で鮭が食べられているそうです。
鮭以外にも、青森県ではウニとアワビのお吸い物の「いちご煮」、秋田県は「ハタハタ」という魚を酢、塩や野菜と漬け込んだ「ハタハタ寿司」、宮城県は「カレイの煮付け」、山形県は「鯉のうま煮」などがあります。
関東で鮭以外を食べるのが、茨城県のフナの甘露煮、千葉県のハゼの甘露煮、岐阜見は焼き鰯を、静岡県ではスズキの仲間のブダイを煮付けにして食べます。
一般的に東日本の年取り魚は鮭とされていますが、県によってもいろいろと違います。
他に東日本のおせちで西日本と違うのは、「祝い肴三種」です。
「祝い肴三種」とは一の重に詰められる、「豊作、子孫繁栄、健康・勤勉」の願いが込められている物です。
関東の祝い肴三種は「数の子」「黒豆」「田作り」となっています。
どれも定番ですが、それぞれにはこんな意味があります。
「数の子」数の子は数万の卵があるので、子孫繁栄
「黒豆」マメに元気に働けるように、健康や長寿
関東では黒豆を「シワがよるまで元気に働けますように」としわができるように煮ます。
「田作り」カタクチイワシを昔に田んぼの肥料としていたので、豊作祈願の意味があります。
東日本と西日本のおせちの中身は「味付け」「年取り魚」「祝い肴三種」に違いがあります。
続いては、西日本(関西)のおせちの具材について詳しく見ていきましょう♪
おせちの地域差!西日本のおせちの具材は?
東日本のおせちの味付けは濃口醤油を使う濃い目の味付けになっています。
西日本は関西を中心に、昆布や煮干し、かつおなど組み合わせ出汁を取るので、
「出汁」の味がメインとされています。その為、薄めの味付けとなっています。
次に年取り魚はどうでしょうか?
東日本の年取り魚は鮭でしたが、西日本の年取り魚は「ブリ」です。
「ブリ」は成長していく中で、名前が変わるので「出世魚」とされています。
このことから、西日本ではブリがお正月の「年取り魚」として一般的に食べられています。
もちろん、場所によって違いもあります。
大阪では「にらみ鯛」を食べます。
「めでたい」の語呂合わせから、鯛だそうです。
にらみ鯛と聞くと「にらんでいる顔のこわい鯛?」と思いますが、そうではありません。
お正月の3日間は神様へのお供え物なので、食べられません。
にらみながら我慢して、4日目に食べることから、「にらみ鯛」と言われています。
他にも、面白いのは島根県の「ワニのお刺身」
ワニといっても、ゴツゴツしているあのワニではありません。方言で「サメ」のことだそうです。
このことを知らないと、びっくりしてしまいます。
とても柔らかく美味しいらしいです。
山口県のふぐや長崎県の鯨など特産や場所にちなんだ魚を食べるところもあります。
そして「祝い肴三種」ですが、関東は「数の子」「黒豆」「田作り」でした。
関西の「祝い肴三種」は「数の子」「黒豆」「たたきごぼう」となっています。
子孫繁栄や健康、長寿を願う「数の子」「黒豆」ほ同じですが、東日本と違い西日本では「黒豆」をシワがないのを不老とし、艶が出るように煮ます。
さらに西日本では「田作り」ではなく、「たたきごぼう」が「祝い肴三種」に入っています。
ごぼうは土の中に長く根をはるので、家の土台が固くしっかりするようにと願う意味があります。
なぜ、西日本ではごぼうなのかというと、大阪や京都など関西にごぼうの有名な産地なことが理由です。
「祝い肴三種」はどの食材も日持ちのする乾物なので、運びやすく全国に広まりました。
東日本と西日本では、土地の自然や歴史などから、おせちの中身にいろいろな違いがありました。
他にも、お重の詰め方も違うなど、まだまだ違いがあるみたいです。
おせちにも地域差がある?具材の違いや特徴を紹介!
今回は、東日本と西日本のおせちの地域差や具材の特徴をまとめてみました。
東日本と西日本でそう変わらないものもあれば、全く違うもの、その土地の特産品もありました。
最近は、お取り寄せできるものもたくさんあるので、気になったものをお取り寄せして、お正月にみんなでいつもと違う物を話しながら、食べるとより楽しいお正月が過ごせそうです♪

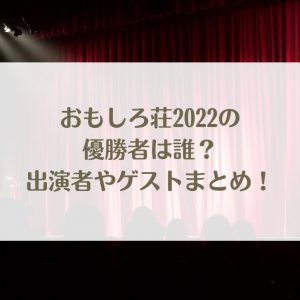
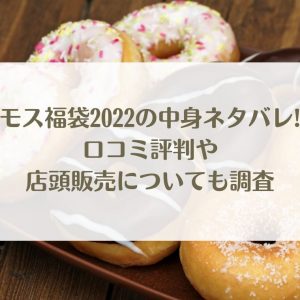






コメント